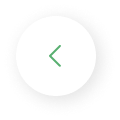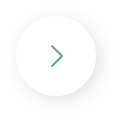防除について②
ー物理的防除の具体的な方法ー
病害虫

目次
光、熱などにより、病害虫の被害を減少させる方法を物理的防除法といいます文献1)。本記事では、防除体系を構成している防除法のうち、物理的防除の施設園芸での具体的な方法をご紹介します。
(1)光を用いた物理的防除
特定波長の光を発するランプ等を用い、害虫や植物の光に対する反応を利用して行う様々な物理的防除法があります。以下に代表的な防除法についてお示しします。
黄色光の利用
ハスモンヨトウやオオタバコガなど、夜行性のガ(ヤガ類)などの防除に一般的に利用されているのが黄色光です。夜行性の害虫には、一定以上の明るさになると行動を停止する性質があり、黄色の光でヤガ類に昼間と勘違いさせ行動を抑制し、作物への被害を防止するものです。黄色光(570nm付近の波長)を発するLED等の黄色灯をハウスの天井面に設置し、吸汁や産卵は夜間に行うヤガ類に対して夜間照明による防除効果が期待されます文献2)。黄色灯は古くから蛍光灯のものが利用されており、近年は棒状LEDの他、電球型LEDが利用されています。

赤色光の利用
ミナミキイロアザミウマなどのアザミウマ類の防除法として開発されたのが、赤色光のLEDを利用してアザミウマ類の活動を制御する方法です。アザミウマ類はハウス内に侵入し作物の葉を食害したり産卵を行いますが、葉へ日中に赤色光(ピーク波長660nm付近)を照射すると葉に定着しにくい性質があります文献3)。また夜間での葉への赤色光の照射によりアザミウマ類が誘引される逆効果があり、日中でもすでに葉にアザミウマ類が定着していると赤色光の照射を行っても効果は無いということが示されています。文献3)には具体的な赤色光の照射パターンとして、日中12時間程度をあげており、最低気温が20℃を超える時期には日出1時間前から日没1時間後までをあげています。
紫外線(UV-B)の利用
紫外線のうち中波長域となるUV-B(280〜315nm)を利用した、イチゴにおけるうどんこ病やハダニ類 の防除法があります文献4)。UV-Bの照射により作物に防御関連遺伝子の発現が確認され、またイチゴではUV-B照射によりうどんこ病抵抗性の発現も確認されました。この結果を利用し専用のUV-B照明器具が開発され、さらに低コスト化された電球型のものも開発されて防除用の器具として販売が行われました。また反射シートを株の下に敷設し葉裏面にもUV-Bが照射可能とすることで、うどんこ病の他にハダニ類の防除も可能となり、イチゴ栽培での主要な病害対策として普及が進むようになりました。さらに、UVB照射と光反射シートを組み合わせることで、うどんこ病とハダニの同時防除が可能となりました。UV-Bは夜間3時間の照射後、日出前に停止するパターンでハダニの卵のふ化を抑制する効果があるとしています。

(2)資材による物理的防除
ハウスや露地での園芸作物の栽培で用いる資材には、直接的な防除効果を狙ったものが多く開発されています。その例を下記に示します。
防虫ネットの利用
ハウスの開口部(換気窓)に展張する網目状の通気性資材で、害虫の侵入を物理的に防止するものです。近年はトマトの重要病害であるトマト黄化葉巻病を媒介するコナジラミ類(シルバーリーフコナジラミ)などの侵入防止のために、非常に細かい目合い(0.3~0.4mmメッシュなど)のものが使用されています。そのため通気性とのトレードオフによりハウス内の高温対策に影響が生じるようになりました。防虫対策を行いながら通気性を維持するには、強制換気文献5)を行うことや、細かい目合いでありながら細い繊維で作られた防虫ネットを選択することが考えられます。また最近のオランダ型の高軒高ハウスであるフェンローハウスでは、高い位置での害虫侵入リスクが少ないこと(ゼロでは無い)から天窓にあえて防虫ネットを展張しないケースも見られます。さらに0.75mmメッシュなど目合いを広げながら害虫を忌避する微量の薬剤をネットに使用したもの文献6)なども開発されています。
近年は赤色防虫ネットの普及がみられます。アザミウマ類やスリップス類は赤色を視覚的に認識できず、ハウス内への侵入を防ぐ効果があるといわれています。またネットの目合いを大きくし通気性を向上させた赤色のものでも防除効果が確保できると考えられます文献7)。
反射性シートの利用
ハウスの周囲や開口部付近の地表面に、一般的な黒色系防草シートのかわりに光を良く反射する白色系シートを展張する例がみられます。また柑橘類の栽培でもマルチ資材に同様な反射性の白色系シート(タイベックなど)の利用がみられます。これらは雑草への防草対策とともに、光の反射による害虫の行動かく乱と飛来抑制を狙うもの、また同時に光の有効利用(光合成促進)を狙うものとして利用されています。前述のUV-Bランプと光反射シートの組み合わせのような複合的な防除方法も考案されています。
UVカットフィルムの利用
UVカットフィルムは380nm以下の波長の紫外線の透過抑制するフィルムのことで、ハウスの外張り被覆資材として用いられる農POや農ビで病害虫防除効果のあるものとして商品化がされ、アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類、ハモグリバエ類などの害虫の発生抑制が期待されます。文献8)では、『紫外線透過能が異なる被覆資材の下でオンシツコナジラミの移動行動を観察した結果、「野外に生息しているオンシツコナジラミは,紫外線カットフィルムを被覆した施設内への侵入が抑制され、侵入しても野外に向かって再び移動する」という行動パターンが推測されている』としています。その他、UVカットフィルムには、灰色カビ病や菌核病などのある種の病原糸状菌における胞子形成の抑制効果もあるとされています文献9)。
粘着資材の利用
粘着資材とは、粘着性のテープ状や板状のもので、黄色や青色に着色されたものになります。特定の色による病害虫の誘引効果(アブラムシ類、コナジラミ類など:黄色系、アザミウマ類など:青色系)と粘着効果により、これらの資材をハウス周囲やハウス内に設置するだけで防除効果を得ることが可能となります。文献10)にはハウスの様々な部位における粘着資材の設置について記されています。

(3)太陽熱による物理的防除
ハウス内で作付終了後の夏期に土壌に潅水を行い、表面に透明フィルムを展張して密閉状態とし、高温による有害土壌微生物の殺菌を行う方法で、太陽熱消毒、太陽熱土壌消毒と呼ばれています。安価に殺菌が可能な防除法となりますが、十分な消毒期間と日射量(太陽エネルギー)の確保が必要で、それらが不十分な場合にはフィルム被覆下の地温上昇も確保できず期待する殺菌効果が得られなくなります。その問題を解決するため、土壌還元消毒という防除法が開発されています。これは有機物を土壌に混和し太陽熱消毒を行うもので、大量に発生する微生物により土壌が還元状態になり、また同時に発生する有機酸による作用により、比較的低温においても殺菌効果が得られる方法となります。また低濃度エタノールを用いた土壌還元による土壌消毒法文献11)も開発されています。
(4)今後の展開
以上のように、物理的防除におけるさまざまな防除方法をご紹介しました。各々は目的や利用場面も異なるものですが、一部を組み合わせたり、他の化学的防除や天敵利用などの生物的防除などと組み合わせて利用するケースも多くみられます。減農薬を行いながら防除効果を得るには物理的防除は必要な手段となっており、また他の防除法との組み合わせによってお互いのメリット、デメリットを補い合うような用法も考えられます。
参考文献
1)物理的防除法(虫害)、農研機構 NAROPEDIA
2)向坂信一、黄色光による夜行性ガ類の忌避、環動昆第13巻第3号 157 ~ 162 (2002)
3)赤色LEDによるアザミウマ類防除マニュアル、(株)光波、(地独)大阪府立環境農林水産総合研究所、静岡県農林技術研究所、農研機構(2019)
4)紫外光照射を基幹としたイチゴの病害虫防除マニュアル~技術編~、農研機構中央農業研究センター(2019)
5)ハウスの換気装置について③ ー強制換気装置ー、ゼロアグリブログ
6)園芸用施設への微小害虫の侵入を抑制する新防虫ネット、農研機構農村工学研究部門
7)赤色防虫ネットによるミナミキイロアザミウマ侵入対策、キュウリ栽培での悩み 「キュウリ黄化えそ病」対策について②、ゼロアグリブログ
8)太田泉、紫外線カットフィルムによる害虫防除のメカニズム、JATTAFジャーナル 4巻・7号(2016)
9)紫外線カットフィルム、農研機構 NAROPEDIA
10)粘着ロールテープ等を活用した夏秋トマト栽培の実証、三好地区環境負荷低減技術普及推進協議会(2024)
11)低濃度エタノールを利用した土壌還元作用による土壌消毒実施マニュアル (第1.2版)、農研機構(2021)

■執筆者:農業技術士 土屋 和(つちや かずお)
育苗装置「苗テラス」の開発など農業資材業界での経験を活かし国家資格の技術士(農業部門)を2008年に取得、近年は全国の施設園芸の調査や支援活動、専門書等の執筆を行っています。