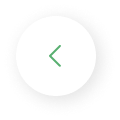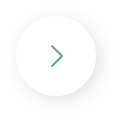防除について①
ー化学的防除の具体的な方法ー
病害虫

目次
農作物の病害虫防除には、化学的防除、耕種的防除、生物的防除、物理的防除などの手段があります。また病害虫発生の様相や、農薬の特徴、栽培事情やコストなど、さまざまなファクターを踏まえ効果的な防除を実施するため、防除法、防除薬剤、防除体制などを体系化し、防除体系が組まれています文献1)。
本記事では、防除体系を構成している防除法のうち、化学的防除の施設園芸での具体的な方法をご紹介します。化学的防除は生物農薬以外の化学物質の農薬を使い、病害を防除する方法のことです。対象となる作物と病害虫への登録農薬を用い、様々な方法により作物や害虫に農薬を付着させて防除が行われます。
(1)動噴と散布ノズルによる有人防除
最も一般的な防除方法として、薬液タンクに希釈した農薬をため、動噴(動力噴霧機)によりチューブを経由して散布ノズルへ高圧で送り、ミストとして農薬を散布する方法になります。散布ノズルは複数個が散布竿などと呼ばれるアームパイプに配置されたものが一般的です。防除作業者がアームパイプを持ち、畝間を移動しながらアームパイプを手振りして防除作業を行います。防除面積が広ければ作業は長時間となり、また防除服や防除マスクを装着しての作業となり、特に高温時には作業者への負担が高いものになります。
参考:スプレーアクセサリー 2024.4月、(株)丸山製作所 WEBサイト
リンク先確認:2024年9月21日
また手振りによる防除作業ではなく、カートや手押し台車などにアームパイプを複数取り付けて人力で移動を行いながら防除を行う形もみられます。これを自動走行化したものが、防除ロボット(自走式防除機)と呼ばれています。

(2)静電散布機による防除
静電散布機とは、農薬の散布粒子を帯電させ、静電気の力で作物体に付着させる散布機のことです文献2)。葉裏や葉茎の込み入ったところにも薬剤の付着がしやすく、効率的な防除によって農薬使用量の低減につながるものです。施設園芸で用いられる静電散布機はノズル先端部に電極を取り付けたもので、高電圧を与えながら農薬散布を行います。前述の手振りによる有人防除や、カート式にセットされたものによる有人防除、後述の自走式防除機による無人防除との組み合わせがあります。
参考:静電ノズル、有光工業(株) WEBサイト
リンク先確認:2024年9月21日
(3)くん煙防除による無人防除
くん煙とは、有効成分と発熱剤、助燃剤を組み合わせて缶や紙筒(発煙筒)に入れたくん煙剤を、燃焼させたり熱源を用いて有効成分を気化させたりして雑菌・殺虫を行うことです文献3)。またくん煙剤は、加熱によって有効成分を煙状の微細な粒子として空中に拡散し、作物の表面に付着させ、 あるいは病害虫に直接接触・吸入させて効力を発揮 させる薬剤です文献4)。
参考:日本曹達(株)、農業用くん煙剤の現況について、農業新時代 第5号(2024)
リンク先確認:2024年9月21日

(4)自走式防除機による無人防除
トマトやパプリカの高軒高ハウスでの栽培では、栽培ベッドの畝間にレールが設置され、その上を自動で往復走行する自走式防除機が良く利用されています。ハイワイヤー栽培と呼ばれる高い位置での誘引がされ、群落の高さも誘引位置に応じて上へと伸びるため、ノズルを取り付けたアームも垂直方向に長いものが取り付けられます。また防除機本体にチューブを取り付けて、遠方に置かれた薬剤タンクや動噴から薬液を送り出す形になります。
参考:オートランナー レールタイプ・ハイワイヤー対応タイプ、有光工業(株) WEBサイト
リンク先確認:2024年9月21日
なお自走式防除機では、畝間から次の畝間への移動は人の手による操作が一般的に必要になります。近年は畝間移動の自動化も可能で、遠隔操作やポンプなどとの連動も可能な次世代型の製品も開発されています。
参考:GPS の使えないビニールハウス内でも自動走行で防除可能 自動走行型スマート農薬噴霧ロボット 「スマートシャトル」をクボタアグリフロントにて展示開始 2024年4月30日、(株)丸山製作所 WEBサイト
リンク先確認:2024年9月21日
(5)常温噴霧機による無人防除
常温煙霧は専用の常温煙霧機を用い、少量の濃厚薬液をハウス内に散布する方法です。散布中は無人防除となり、また散布量も少なく湿度の上昇を抑えることが可能となります文献5)。少量散布のため、薬害発生も起こりにくい方法と言えるでしょう。常温煙霧機は、薬液タンク、コンプレッサ、煙霧ノズル、送風機から成り、送風ファンにより薬液の微粒子をハウス内にくまなく噴霧を行う機能を持ちます。操作はタイマーにより行い、夜間防除も可能になります。また、常温噴霧機と循環扇を併用するケースもみられます。
参考:ハウススプレー、有光工業(株) WEBサイト
リンク先確認:2024年9月21日
常温煙霧では薬液が直接果実に当たると汚れの原因になるため、送風方向などに注意する必要があります。また散布終了後は換気を行ってからハウス内に作業に入る必要があります。使用する農薬は常温噴霧用に登録された専用のものに限られますが、近年は登録農薬が増加傾向にあります文献6)。

(6)高濃度CO2によるイチゴ苗のくん蒸
イチゴ栽培では、苗から広がりやすいハダニの被害が問題となっています。イチゴ産地の栃木県では密閉空間に置かれたイチゴ苗に対して高濃度CO2を長時間施用することでハダニへの高い防除効果が得られることを明らかにしました文献7)。処理による悪い影響もみられず、高濃度CO2くん蒸装置も製品化がされ、農薬耐性が付きやすいハダニにおける効果的な防除方法として実用化がされています。そこでは本圃でのハダニ防除のための化学農薬散布回数も低減されるメリットもみられます。なお使用する液化CO2ガスは農薬登録されたものに限定されます。
参考:二酸化炭素くん蒸剤いちごハダニ殺虫システム、日本液炭(株) WEBサイト
リンク先確認:2024年9月21日
(7)今後の展開
以上のように、化学的防除におけるさまざまな防除方法をご紹介しました。農薬散布作業は人力で行うには負担も大きく、また化学農薬の飛沫を被ばくする可能性もあるため、省力化や無人化、さらには減農薬化のための技術開発と製品開発が進展した分野と言えます。一方で自動収穫ロボットなどが、AIや画像処理を活用した先端技術として近年注目をあびるようになりました。ご紹介したような防除方法における技術開発も同様に、今後の進展が期待されるものと考えられます。
参考文献
1)防除体系、農研機構 NAROPEDIA
2)静電散布機、農研機構 NAROPEDIA
3)くん煙、農研機構 NAROPEDIA
4)日本曹達(株)、農業用くん煙剤の現況について、農業新時代 第5号(2024)
5)常温煙霧、農研機構 NAROPEDIA
6)朝比奈泰志、高知県における常温煙霧法の取り組み、農業新時代 第3号(2022)
7)小山田浩一、高濃度二酸化炭素くん蒸処理によるイチゴの主要害虫に対する防除技術の実用化に関する研究、栃木県農業試験場研究報告 76号(2017)

■執筆者:農業技術士 土屋 和(つちや かずお)
育苗装置「苗テラス」の開発など農業資材業界での経験を活かし国家資格の技術士(農業部門)を2008年に取得、近年は全国の施設園芸の調査や支援活動、専門書等の執筆を行っています。