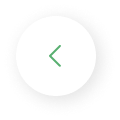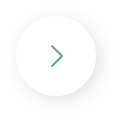防除について③
ー生物的防除での天敵利用ー
病害虫

目次
生物的防除法は近年の減農薬栽培や環境保全型農業の推進においても重要な技術であり、施設園芸でのIPM(総合防除)を構成する技術のひとつになります。生物的防除法の概要について参考文献1)に下記の記述があり、引用します。
この防除法は植物が本来持っている、寄生性、捕食性、誘引性などの性質を防除に利用する方法です。この中には、天敵による害虫の捕食・寄生を利用して害虫の密度を低減させる方法、性フェロモンを用いて害虫の雌雄間の情報伝達をかく乱して交尾を妨げる方法、弱毒ウイルスや非病原菌の接種により病原菌ウイルスや病原菌の感染を防ぐ方法などがあり、製剤化されたものを「生物農薬」といいます。
こうした生物的防除の中で、本記事は天敵を利用した生物的防除について、施設園芸での考え方やポイントをご紹介します。なお、引用内容にあるような「生物農薬」として農薬登録を受け製剤化と販売が行われている天敵の他に、もともと地域に生息する土着天敵の利用も一部では行われています。
(1)国内での天敵導入の経緯
天敵の利用は欧米で先行し、EU内での残留農薬問題と化学農薬に対する規制への解決策の一つとして、天敵とその利用技術の開発が進んだ経緯があります。農産物の輸出入が活発に行われているEUでは、残留農薬の規制も厳しく、その対策は必須のことと考えられます。
国内にはそうした技術が近年導入され、果菜類栽培などを中心に普及がみられますが、欧米とは異なり、国内では病害虫の化学農薬に対する薬剤抵抗性の発達への解決策として導入が進んできたものと考えられます。すなわち化学農薬を利用しても防除が困難な病害虫が多く存在し、その対策の切り札的に天敵利用が拡大している状況と言えるでしょう。こうした経緯については、天敵など生物農薬を販売しているアリスタライフサイエンスの里見純氏による「天敵利用をめぐる海外の動向と我が国における展望」文献2)に詳述されています。

(2)天敵利用でのメリットと留意点
前述の里見氏の文献には、欧米では専門のコンサルタントによる天敵利用に関する指導が行われているが、国内では都道府県の普及指導員やJAの営農指導員が専門家としての指導に当たっているという違いについて述べられています。そこでも里見氏が所属するアリスタライフサイエンスのような専門メーカーによる製品や情報の存在は大きいものと言えるでしょう。
同社のWEBサイト文献3)には、天敵の特徴・メリットについて「薬剤抵抗性害虫への防除効果が高いこと、農業害虫への薬剤抵抗性リスクが低いこと、散布回数の上限がないこと、持続可能な防除暦を計画しやすいこと」をあげています。
また、留意点として「発生病害虫の特定、病害虫の発生(初期)時期の見極め、効果がマイルドなため、病虫発生や病害発症状況の相対的観察」これらを必要とすることをあげています。
これらについては、発生病害虫の特定のこと以外は化学農薬の利用には無いことと言えるでしょう。また国内での天敵利用の機会となっている薬剤抵抗性害虫への防除において、対象となる害虫(ハダニ類、アブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類等)に対応した様々な天敵が利用されています。さらに天敵の利用では、化学農薬と異なり薬剤抵抗性が害虫に付与されるリスクが低く、散布回数制限も無いため、持続的・計画的な利用が可能と言えるでしょう。

(3)天敵利用のポイント
鹿児島県でIPMの研究開発や普及に携わった柿元一樹氏は、「天敵利用を基幹とした IPM を農業経営に取り込む―SDGs 時代の実践的害虫管理―」文献4)で天敵利用のポイントについて次の3点をあげています。
天敵により利用する餌が違うこと
柿元氏は天敵と対象となる害虫について、一つの種で全ての害虫を抑えられる万能な天敵は存在しないとし、例えばアブラムシにはアブラムシを捕食する天敵が,またアザミウマやハダニにもそれぞれの天敵が存在しており、さらにアブラムシにはテントウムシや捕食性のアブやハエ,寄生バチといった様々な天敵が存在することをあげています。こうした多用な天敵を、その捕食性と対象となる害虫に応じて利用する形になります。
異なる特性を持つ天敵をうまく組み合わせること
また柿元氏は天敵の組み合わせについて、ジェネラリストの天敵とスペシャリストの天敵という分類で述べています。ジェネラリストの天敵は多様な餌を利用し、スペシャリストの天敵は特定の害虫のみを捕食するものです。こうした特性の異なる天敵を組み合わせることで効果的な防除が可能になる、という考え方にもとづいた利用法が提起されています。
例えば天敵の餌となるハダニについて、「ハダニだけを捕食するスペシャリストの天敵と、餌としてハダニへの依存度が低く,ハダニ以外の微小な昆虫や花粉のような植物資源を利用するジェネラリストの天敵」について触れています。自然界において多用な天敵が消長を繰り返しており、柿元氏は桑畑での調査において「ハダニがいる時期はスペシャリストを含む多様な天敵が存在」し、一方で「ハダニがいない時期に存在しているのは,さまざまな餌を利用できるジェネラリストの天敵」であるとしています。こうした天敵の食性の違いが防除戦略でのポイントになるとしています。
実際に天敵の餌となる害虫の発生が多すぎると天敵の捕食効果が追いつかず防除効果が得られないこと、逆に天敵放飼時に餌となる害虫の量が少な過ぎると,餌不足となって天敵が作物への定着すらできないというジレンマが発生するとしています。こうした状況を解決したのがジェネラリストの天敵であり、「スワルスキーカブリダニやミヤコカブリダニといった、いろいろな餌を利用するジェネラリストの天敵が登場して,この状況が大幅に改善された」ことに柿元氏は触れています。特にスワルスキーカブリダニについては、アザミウマ,コナジラミ,ホコリダニの3種類の害虫に一定の効果があること、またピーマン等の花粉や蜜を与えただけでも生存可能で増殖もできることをあげ、ピーマンが開花していれば放飼可能なため、生産者に非常に扱いやすい天敵としています。
天敵が働ける住処を人為的に作ること
さらに柿元氏は、圃場に天敵が常に維持される仕組みについて述べています。そこでは「天敵温存植物」や「バンカー植物」の利用が考えられます。鹿児島県の「天敵温存のための有用植物利用マニュアル 」文献5)には、これらについて以下の定義がされており、引用します。
植物が本来有する花粉・花蜜または植物に自然に発生する節足動物を餌として天敵の機能を高めることを目的とした場合を「天敵温存植物」、植物に対して人為的に餌を導入する場合を「バンカー植物」と呼びます。
また、農研機構の安部順一朗氏による「新規登録された天敵タバコカスミカメの上手な使い方と導入事例」文献6)には、コナジラミ類の防除に用いられる天敵「タバコカスミカメ」の利用について以下の記述があり、引用します。
一部の天敵種では、害虫とならない昆虫(代替餌)を、作物とは異なる植物につけて圃場内で維持する「バンカー法」が用いられている。タバコカスミカメの特徴に注目して研究を進めた結果、バーベナやクレオメといった植物(天敵温存植物)を使えば、害虫がいなくともタバコカスミカメを維持・温存できることが明らかになった。
この方法のメリットとして、天敵温存植物のみでタバコカスミカメを維持可能となって、特別に餌を用意する必要もないことを安部氏はあげています。このことから、クレオメなどの天敵温存植物を用いたタバコカスミカメの利用が、タバコカスミカメの農薬登録とともにトマト施設栽培において普及が進んだものと言えるでしょう。
(4)今後の展開
天敵の利用技術は、前述のように専門のメーカーや指導機関、試験研究機関、それに現場の生産者が協力して構築された経緯があります。また導入に当たっては試験圃場での予備試験を経て、現場の施設での実証が行われ、その地域の作物や栽培方法、気象条件や生物相などに対応した利用技術が組み立てられていると言えるでしょう。天敵利用には導入が進んだ地域とそうでない地域もみられますが、生産者や指導機関の熱意や努力がその背景にあるのかもしれません。
また天敵の利用技術では、選択性農薬と呼ばれる特定の害虫グループだけに効果があり、天敵に対する影響が小さい化学農薬をスポット的に使用する方法もみられます。そうした利用技術の開発によって施設園芸におけるIPM(総合防除)や環境保全型農業、さらにはSDGsの取り組みも進んでいると言えるでしょう。
農薬としての天敵の購入費用の負担増がある中で、防除時間の短縮による人件費抑制や、防除負担が減り収穫や管理作業などを確実に行えることでの収益維持といった経済効果も見込まれ、前述の薬剤抵抗性害虫への対策と合わせこれらは天敵導入のポイントと言えるでしょう。
下記の記事も、ぜひご参照ください。
参考)ゼロアグリブログ:ナス栽培での悩み ー害虫防除での天敵利用についてー
参考文献
- 生物的防除法(虫害)、農研機構 NAROPEDIA
- 里見淳、天敵利用をめぐる海外の動向と我が国における展望、植物防疫 第73巻1号(2019)
- 「生物農薬」について、アリスタライフサイエンス WEBサイト
- 柿元一樹、天敵利用を基幹とした IPM を農業経営に取り込む―SDGs 時代の実践的害虫管理―、農業 1671号 2021.4
- 天敵温存のための有用植物利用マニュアル、鹿児島県
- 安部順一朗、天敵タバコカスミカメの紹介とこれまでの技術開発、 新規登録された
天敵タバコカスミカメの上手な使い方と導入事例 講演要旨集(2021)、農研機構

■執筆者:農業技術士 土屋 和(つちや かずお)
育苗装置「苗テラス」の開発など農業資材業界での経験を活かし国家資格の技術士(農業部門)を2008年に取得、近年は全国の施設園芸の調査や支援活動、専門書等の執筆を行っています。