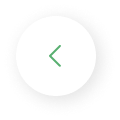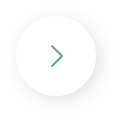無人防除について
ハウス 病害虫

目次
ハウス内の作業において、防護服を着用しホースを引き回しながら行う薬剤散布は、重労働であり、農薬の被ばくも発生しやすく、特に夏場には過酷なもののひとつです。このような防除作業での負荷軽減のため、薬剤散布での自動化や省力化の取り組みが、防除機を開発する機械メーカー等を中心に進められてきました。本記事では無人防除として、こうした製品や仕組みについてご紹介をいたします。
自走式の防除機(防除ロボット)
ハウス内での防除作業は、薬液タンクよりポンプ(動噴)により薬剤をホースを経由して送り、アームに取り付けられたノズルから噴霧する形で行われます。人が長いリールホースを引き回し、アームを上下左右に振りながら作物にまんべんなく薬剤を散布する作業となります。そうした移動と噴霧の作業を機械化、自動化したのが自走式の防除機(以下、防除ロボット)になります。特に大規模施設では必須の装置となっています。
防除ロボットの構造と機能
防除ロボット本体には車輪による自走機能やバッテリーが搭載され、本体から立ち上がったアームにノズルが取り付けられています。ノズルの数やアームの長さは、作物群落の高さに応じて選択できるようになっており、トマトやパプリカ等のハイワイヤー栽培にも対応可能となっています。また本体はリールホースを引っ張りながら畝間を往復移動し、防除を行います。片道での散布、往復での散布など、散布方法の設定が可能なものもあります。防除ロボットはいったん畝間走行での防除を開始すれば特に操作は不要なため、防除での大幅な労力の削減と、作業者の安全性確保が可能となります。なおノズルに静電タイプのものを用いることで、薬剤の付着も良く、散布量の低減も可能となります。
参考:オートランナー レールタイプ・ハイワイヤー対応タイプ、有光工業(株) WEBサイト
土耕栽培、養液栽培と防除ロボットの走行
土耕栽培では、畝間は土壌面となり、防除ロボットはタイヤ式による走行を行う形になります。一方で養液栽培では、畝間にパイプレールが設置され高所作業車等が走行可能な場合、防除ロボットも同様にパイプレール上を車輪による走行を行う形になります。また土耕でのトマト等のハイワイヤー栽培でもパイプレールが設置されている場合もあり、そこでも同様に車輪走行が行われています。走行の安定性や速度の面で、パイプレール上の走行が有利となりますが、整地状態によってはタイヤ走行でも安定的に走行可能な場合もあるでしょう。

防除ロボットの畝間間移動
防除ロボットの畝間間での移動は、自走式の高所作業車等と同様に手動操作が必要となります。そこでの移動をスムースに行えるように、移動用の車輪を別に設けた機種もあります。
また次世代型の防除ロボットとして、畝間間移動も含めてインテリジェントな走行を行う機種も開発されています。圃場内に設置されたタグと本体内蔵カメラからの情報を元にプログラム化された移動を行うもので、ホースの巻き取りや送り出しも行い、本格的な無人防除に対応するものと言えます。
参考: GPSの使えないビニールハウス内でも自動走行で防除可能自動走行型スマート農薬噴霧ロボット 「スマートシャトル」をクボタアグリフロントにて展示開始、丸山製作所 2024年4月30日
害虫防除ロボットに関する研究
研究段階のものとして、害虫(コナジラミを対象)を吸引しながらハウス内を走行するユニークなロボットが農研機構を中心に開発されています文献2) 3)。害虫が気流や振動などを検知し捕食者から回避を行う性質を利用するもので、超音波集束装置と呼ばれるもので離れた位置から害虫に触覚刺激を与え、非接触で葉に付着する害虫を離脱させる仕組みです。離脱後の害虫はLEDの光により誘引され、さらに吸引機と内部の粘着板により捕獲されます。これらの装置が自走式台車に一式で搭載され、タイヤ走行により圃場内を移動しながら無人防除を行うものと言えます。
現段階では実用化の手前にあるようですが、葉裏などに隠れているコナジラミを飛び立させながら捕獲する機能は大変ユニークなものです。夜間稼働時の効果の検証や、装置の省電力化などにも研究で取り組んでおり、期待される技術のひとつと考えられます。
参考:
浦入千宗、害虫防除ロボットに関する研究の紹介 (2025) 、ハイドロポニックス 38(2):4-5
(研究成果) 害虫に超音波を用いた振動を与えて撃退!、農研機構 2023年9月5日
その他の無人防除の仕組み
自走式散布装置
その他の無人防除の仕組みとして、スイッチひとつでハウス内の防除を行う防除設備も実用化がされています。歴史のある設備として、自走式散布装置があります。これは多数のノズルを取り付けたアームが、ハウスの屋根下のレールに沿って往復移動し、薬剤ホースを引き回しながら薬剤散布を行うものです。地面から離れた位置での移動を行うため、安定した動作が可能となっています。また複数のアームを設置することで連棟ハウスであっても圃場全体をカバーできるものです。タイマー等の制御によって完全自動運転化も可能となります。主にベンチ栽培(鉢物、苗物など)や切り花栽培などで利用されています。
参考:自走式散布装置 グリンメイト Rタイプ 多目的システム、株式会社グリーンテック Webサイト
ハウス内の配管による防除設備
ハウス内にくまなく配管をめぐらし、頭上からのミストや薬剤の散布を行う設備で、スイッチやタイマー操作による無人防除が可能です。様々な機能やグレードの設備があり、薬剤散布に特化したもの、散水と薬剤散布を兼ねたもの、細霧冷房と薬剤散布や葉面散布を兼ねたものなどがあり、ノズルの粒径、配管の圧力強度等の仕様が異なります。また実際に多目的細霧システム(細霧冷房と薬剤散布用)や多目的散布システム(散水と薬剤散布用)としての導入が行われています。これらは主に中小規模のハウスで利用されています。
参考:クールミスティ、福栄産業株式会社 Webサイト
常温煙霧機
常温煙霧機は少量の濃厚薬液をハウス内に散布する装置です。散布中はハウスを密閉し、無人防除となります。また散布量も少なく済み、湿度の上昇や水滴の付着も抑えることが可能となります。農薬は常温煙霧機用に登録されたものを用いる必要があります。常温煙霧機は、薬液タンク、コンプレッサ、煙霧ノズル、送風機から成り、送風ファンにより薬液の微粒子をハウス内にくまなく噴霧を行う機能を持ちます。操作はタイマーにより行い、夜間防除も可能になります。また、常温噴霧機と循環扇を併用するケースもみられます。
参考:常温煙霧機 LVHシリーズ 無人散布システム、有光工業株式会社
今後の展開
以上のように無人防除の仕組みとして、自走式のロボットやアームを用いるもの、固定式の配管によりハウス全体をカバーするもの、常温煙霧機のような特殊な方法によるものなど、様々な形があります。いずれも設備コスト、導入コストがそれなりに必要となり、防除作業の負荷や作業者への負担の軽減、導入による労力や労務費の削減といった観点で、導入のメリット、デメリットを検討する必要があるでしょう。
一方で費用を要する機械設備の導入は行わず、作業負担は発生するものの防除作業を簡易に行える装置も存在します。一例として手押し式のアームによる防除機で、複数の畝をまたぐようなアームを手押し台車に取り付け、押しながら防除を行うものです。導入費用も抑えられ、押すだけの作業で負荷も低減されます。このような有人防除や無人防除など、様々な防除方法があり、用途や予算に応じ選定が可能と言えるでしょう。

■執筆者:農業技術士 土屋 和(つちや かずお)
育苗装置「苗テラス」の開発など農業資材業界での経験を活かし国家資格の技術士(農業部門)を2008年に取得、近年は全国の施設園芸の調査や支援活動、専門書等の執筆を行っています。