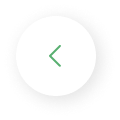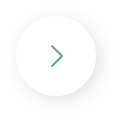ニガウリの生産動向と栽培の特徴について
栽培

目次
ニガウリ(ゴーヤ、ゴーヤー、レイシ)はウリ科の野菜で、つるは細く旺盛に分枝し、生育適温は25~30℃で高温多湿を好み、乾燥にも強い植物です。独特の苦味と豊富なビタミンC含量、苦味成分の機能性などが注目されています文献1)。また耐暑性が強く、高温期でも栽培が容易です文献2)。本記事ではニガウリの生産動向と栽培の特徴を中心にご紹介します。

ニガウリの生産動向
令和4年産(2022年) の調査では、全国のニガウリ作付面積 600ha のうち、約 1/3 を沖縄県が占め、収穫量も同様に約 1/3 を占めています。作付面積では鹿児島県、宮崎県、群馬県、長崎県が続き、これら上位 5 県で 528ha となり、全国の約 88% を占めます。また上位 5 県の収穫量の合計は 13,330t で、全国での 15,000t の約 82% を占めます。このようにニガウリ栽培はこれら 5 県で産地形成が進み、特に沖縄が全国最大の産地となっています。また 5 県のうち群馬県のみが関東地方にあり、他は温暖な九州沖縄地方にあります。群馬県ではキュウリ産地での夏場の補完作物として、おもに露地栽培で栽培が拡大した経緯があります文献3)。
| 都道府県 | 作付面積 (ha) | 収穫量 (t) | 出荷量 (t) | 収量 (t/10a) |
| 沖縄 | 218 | 5910 | 5030 | 2.7 |
| 鹿児島 | 96 | 1800 | 1600 | 1.9 |
| 宮崎 | 81 | 2520 | 2490 | 3.1 |
| 群馬 | 69 | 2000 | 2000 | 2.9 |
| 長崎 | 34 | 1110 | 1080 | 3.3 |
| (全国) | 600 | 16200 | 15000 | 2.7 |
ニガウリ栽培の 10a 当たり収量は、全国平均の 2.7t に対し、沖縄県が同じく 2.7t で、宮崎県、群馬県、長崎県はそれを上回り、鹿児島県が 1.9t と低いものになっています。各地の気象条件や作型、品種、栽培方法には異なるものがあり、それらが単収の違いに影響を及ぼしていると考えられます。
なお、対令和 2 年産(2020年)での令和 4 年産の全国作付面積は 90% と大きく減少しています。都道府県別でみると、沖縄県が 82.9 %、鹿児島県が 88.9 %、宮崎県が 98.8% 、群馬県が104.5% 、長崎県が 103.0% となっています文献4)。最大産地である沖縄県の減少率が最も大きく、単収の高い群馬県と長崎県は逆に作付面積が増える傾向にあります。このことから、単収の増加が収益性の向上や作付面積の拡大に寄与していることが示唆されます。
ニガウリの作型と周年供給
ニガウリの作型は多岐にわたり、各地で複数の作型を組み合わせる例もみられます。全国的に行われる普通栽培は、春先に定植し、6 月~ 9 月に収穫します文献2)。沖縄県での普通栽培は、6 月から 10 月まで収穫します文献5)。沖縄県や宮崎県での促成栽培は、10 月~ 11 月に定植し、年末から5~6月頃まで収穫します文献5)6)。また沖縄県や鹿児島県の奄美地域での促成栽培は、無加温での栽培が可能です。宮崎県での促成栽培は、暖房機での加温による栽培が行われています。長崎県での半促成栽培は、3月に定植し、5 月~ 7 月を中心に収穫します文献7)。また沖縄県での半促成栽培は、2月~3月に定植し、4 月 から 9 月まで収穫します文献5)。このように全国的には、ほぼ年間を通じてのニガウリの収穫が可能になっており、市場への周年供給が行われています。
ニガウリ栽培のポイント
草勢管理による多収化
ニガウリは定植後 1 月程度は摘心を行わず無整枝とし、根の伸長を促すことで着果開始までに草勢を強くする必要があります。また初期の雌花は除去し、草勢を維持します文献8)。またニガウリには様々な整枝・誘引の方法があり、垂直誘引や斜め誘引、扇誘引、棚仕立てなどの誘引法が行われます。いずれも親つるの摘心後に子つるを誘引し、さらに子つるを誘引して節数を確保しつつ、1 つる当たりの適正な着果数に管理します。ニガウリは各節ごとに着花するため、多収化には摘果等により着果負担と草勢のバランスを取ることが必要になります。
交配作業
露地での普通栽培では訪花昆虫による受粉が行われ、昆虫の活動が低下する時期や、花粉の捻性が低下する高温期には交配(人工受粉)作業が行われます。またハウス栽培では交配が基本になります文献8)。交配作業には、その時期などの調整によって、着果数と草勢のバランスを取る意味合いもあります。沖縄県では、低温期に花粉捻性が低下する問題に対し、花粉の長期保存技術を開発し、マニュアルを公開しています文献9)。同マニュアルには、花粉の保存と利用の詳細な方法が記載されています。
低温期の温度管理
定植時に低温に遭遇する促成栽培や半促成栽培では、保温による地温の確保(18 ℃以上)により草勢を強くし、早期に収穫を開始する必要があります文献2)。草勢が確保されず着果した場合には、着果負担により収量が低下する恐れがあるため、着果時期の調整などが必要になります。またハウス内温度を花粉捻性低下や生育不良の防止のため日平均15 ℃以上とするよう、日中の換気装置の調整等による温度確保が必要になります。
潅水と施肥
ニガウリは比較的乾燥に強い植物ですが、葉数が多く葉面積が大きいため、蒸散量も多く適切な潅水による水分供給が必要になります。水分不足により果実肥大が抑制されることもあり文献8)、また連続した収穫も行われるため、点滴潅水や少量多潅水と養液土耕栽培による施肥が有効と言えるでしょう。
ニガウリ栽培についての様々な取り組み
年々、猛暑が頻発し、夏期の野菜栽培や施設栽培が困難となる中で、耐暑性が高いニガウリは猛暑に対応可能な作物として注目されており、農畜産業振興機構が発行する月刊誌「野菜情報」でも各地の栽培事例などが頻繁に取り上げられています。例えば、関東地方で最も猛暑が厳しい地域の一つである群馬県館林市周辺において、ニガウリ栽培が主産のキュウリに次ぐ作物として産地化がされており、ハウス栽培ではドローンによる遮熱剤塗布での高温対策なども進められています文献10)。また主産県の沖縄では、県内第 3 位の産地である糸満市において地産地消の取り組みも進められています。これは県外への輸送運賃の高騰に対応し、那覇市に至近の立地を活かしたもので、加工業務用途の需要開拓も行われています文献11)。
ニガウリは比較的病害に強い作物とされていますが、沖縄県では重要害虫として、ミナミキイロアザミウマ、タバココナジラミが挙げられ、薬剤感受性の低下がみられるこれらの防除が課題となっています。そのため石垣島や糸満市では両害虫の対策として天敵生物のスワルスキーカブリダニを用いた実証展示圃を設置し、その高い防除効果が確認され、普及が拡大し生産者の収量と所得の向上につながっています文献12)。
最後にニガウリの育種については、種苗会社によるものと公設試験場によるものがあり、地域や作型に応じた様々な品種が育成されています。近年は苦味の少ないマイルドな食味のものも育成されており、需要に応じた生産に寄与するものと考えられます。
参考文献
- 「ニガウリ」、NAROPEDIA
- 田中義弘 「作型と栽培の要点」、農業技術体系 野菜編 第 1 巻 ニガウリ 基礎編 (2013)
- 長浜ゆり 「百成レイシ2号・無加温ハウス栽培」、農業技術体系 野菜編 第 1 巻 ニガウリ 精農家の野菜栽培技術 (2013)
- 「今月の野菜 ニガウリの需給動向」、野菜情報 2024.8
- 新垣かおる 「今月の野菜 産地紹介:沖縄県 JAおきなわ南部地区 ~沖縄の太陽を浴びた夏野菜ゴーヤーの生産~」、野菜情報 2020.8
- 宮崎県産農畜産物「ゴーヤー」、JAみやざき
- 長崎県農林業基準技術「にがうり(半促成)」、長崎県農業イノベーション推進室
- 田中義弘 「本圃」、農業技術体系 野菜編第1巻 ニガウリ 基礎編 (2013)
- ゴーヤー技術マニュアル「ゴーヤーの低温感受性と花粉の長期保存技術」、沖縄県農林水産部
- 玉岡竜吾 「今月の野菜 産地紹介:群馬県 JA邑楽館林 ~猛暑に負けないにがうり栽培~」、野菜情報 2024.8
- 片倉杉夫 「調査・報告 沖縄県糸満市におけるゴーヤーの産地振興と新規就農者の取り組みについて」、野菜情報 2022.11
- 協同農業普及事業の成果事例(令和5年度)「沖縄本島南部地域のゴーヤーにおけるスワルスキーカブリダニを用いた害虫防除の取組」、農林水産省

■執筆者:農業技術士 土屋 和(つちや かずお)
育苗装置「苗テラス」の開発など農業資材業界での経験を活かし国家資格の技術士(農業部門)を2008年に取得、近年は全国の施設園芸の調査や支援活動、専門書等の執筆を行っています。