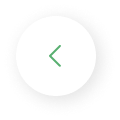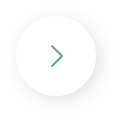養液栽培(水耕栽培を含む)、養液土耕栽培、ゼロアグリ
それぞ れの特徴を比較
養液土耕栽培 養液栽培

目次
栽培方法の分類に養液栽培、養液土耕栽培といった区分があります。ゼロアグリは大枠では養液土耕栽培のひとつに分類されますが、またゼロアグリには養液栽培と養液土耕栽培の良い点を兼ね備えた特徴もあります。(よく言われる「水耕栽培」は固形培地を使用しない養液栽培を指します。)
養液栽培のあらためて養液栽培、養液土耕栽培、ゼロアグリの特徴、それぞれの特徴を◎、〇、△、×などを付けながら整理してみます。

養液栽培の特徴

◎均一性
土壌に比べ保水性、排水性など均一性の高い人工培地を用いるため、生育も均一に保つことができます。ただしハウス内環境は必ずしも均一ではないため、その影響が生じることもあります。
〇制御性
植物が必要とする水分や養分を正確に制御して与えることができます。ただし制御の設定が正しくない場合には期待する効果が得られない場合もあります。必要量を与えることでストレスフリーな栽培を実現し、ま。た逆に水分を絞るなどでストレスを与えて糖度など品質を向上することも可能です。必要とする水分や養分は、日射量、葉面積、生育ステージなどで決まり、それらの要因を考慮した制御が求められます。
〇作業性
土耕栽培で行うような大掛かりな土壌消毒は不要です。またベンチ上での栽培で収穫位置や作業位置を調節でき、低位置でかがみ込むような動作もなく、作業性は良好です。
〇栽培期間延長
栽培終了から次期定植までの作替え期間を短縮でき、その分の栽培期間の延長と収量増が期待できます。計画的に手際よく作替えを行えば1週間程度で終了することも可能です。
〇衛生環境
床面に防草シートやマルチを前面に敷くことができ、クリーンな作業環境と栽培環境を保持できます。
△技術習得
機器の操作や制御設定、養液管理、メンテナンスなど、様々な技術を体系的に習得する必要があり、初心者にはハードルが高いケースも見られます。
×高コスト
栽培ベンチ、給液装置や培地加温装置などの初期投資が必要になります。一度設置すると改変は難しく、作物や栽培法に合わせた設計も必要となります。
養液土耕栽培の特徴
◎安定性
養液栽培の比較的少量の培地に比べ、水分や肥料分のバッファーを持つ土壌での栽培には安定性があります。潅水系のトラブルがあっても、生育にすぐに影響が出ることはありません。
◎低コスト
簡単なタイマー制御方式の養液土耕栽培装置など安価な機器もあります。ただし養液栽培のような高度な制御性を求めることはできません。
〇土壌の特性を生かした栽培
ミネラル分などを含む土壌の特性を生かした食味の向上を目指す栽培も多く見られます。また土壌微生物の力を活かした栽培も有機農業などで取り入れられています。
△作業性
地面付近で行う収穫作業や管理作業、高温期の消毒作業など重労働や負担の大きい作業が多くあります。
×連作障害
連作障害は特にハウス栽培で発生しやすく、土壌消毒や土壌改良、抵抗性品種や接ぎ木利用などが必要になります。
ゼロアグリの特徴

◎安定性
養液土耕栽培での土壌による安定性と、養液栽培に近い植物にとってのストレスフリーな給水や施肥制御の双方が実現でき、安定した栽培が特徴となります。
〇低コスト
養液栽培に比べ1ケタから2ケタ少ない投資で導入が可能で、サブスクを利用することで初期投資の軽減も可能です。
〇土壌の特性を生かした栽培
養液土耕栽培と同様に土壌の特性を生かした特徴的な栽培も可能です。
◎簡易な制御性
AIによる潅水制御など、学習機能により使いこむほど賢くなる特徴があり、制御の設定も簡便です。
◎発展性
地下水位や天候、潅水量、生育ステージなどに関わらず、作物が要求する窒素量を、簡単な設定で自動的に安定調整する機能(施肥量オート調整)が開発されました。このような最新の機能がクラウドサービスとして提供される発展性が特徴です。
今後の展開について
ゼロアグリの特徴として、養液栽培のメリット(制御性)、養液土耕栽培のメリット(安定性)の双方を兼ね備え、それを低コストで簡易に実現することがあります。いわば良いとこ取りの栽培方法とも言えます。導入も簡易で、AIを用いた制御により技術習得のハードルも低いと言えるでしょう。
また新機能の「土壌溶液EC定値制御」では、この土壌溶液EC値をあらかじめ設定した目標値に近づけるよう自動制御する機能があるなど、今後の進化と発展も期待されます。
※ゼロアグリの使用環境として土壌の特性(土質と排水性や地下水位など)を考慮する必要があります。