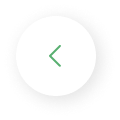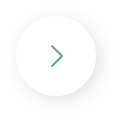熱帯果樹の栽培 ーマンゴー栽培についてー
栽培

目次
マンゴーは世界的に生産が行われている熱帯果樹の1つです。国内では沖縄県、宮崎県を筆頭に、鹿児島県や熊本県など温暖な地域で栽培が行われていますが、北海道でも少量ですが栽培がされています。芳醇な香りと濃厚な甘さが特徴のマンゴーは贈答品として利用されて、高級フルーツのジャンルに入る果実です。輸入品も多く流通していますが、国産の鮮度や安心感、品質の高さが評価されており、輸入品に負けない生産と流通が行われていると言えるでしょう。本記事では、マンゴー栽培の概要、および代表産地である沖縄県と宮崎県でのマンゴー栽培についておもに技術面でご紹介します。
マンゴー栽培の概要
マンゴーは熱帯アジア原産の果樹で、メキシコやフィリピン、タイなどで生産された果実が輸入されています。国内では沖縄県が温暖な気候を利用して最も早く栽培に取り組み、現在でも国内トップの産地となっています。降雨による炭そ病の被害を受けやすいため最低でも雨よけ施設が必要で、沖縄県ではハウスでの無加温栽培が中心となっています。宮崎県では加温栽培が行われ、早期出荷や高品質果実による高単価での販売が進められています。
品種と栽培適温、出荷時期
マンゴーの主要品種には赤系のアーウィンがあり、収穫期には果皮が濃い赤色となり落果するため、ネットを用い果実を包み収穫を行います。また緑系のキーツなどは落果はせず、成熟果を収穫した後に追熟を行います。代表品種であるアーウィンでは、花芽分化に10~12度程度の温度帯が適しており、生育適温は25~30℃程度となります。一方で冬期の最低生育温度は5℃以上が求められ、本州以北では加温栽培が必要となり、積極的な加温により早期出荷も可能となります。アーウィンは早生系で加温栽培に適した品種です。また中生やキーツなど晩生の品種もありますが、秋期以降は輸入品の流通が主流になっています。
誘引と着果、果実の管理
マンゴーは苗木の定植から収穫まで最低で3年を要し、5年目頃に本格的な収穫期となります。マンゴーの栽培管理で特徴的なこととして水平方向への主枝等の誘引があり、本来は高木となるマンゴーの高さを抑えた管理をしています。新梢の発生数は水平方向への誘引により抑えられますが、新梢への養分の蓄積も進んで冬期の低温遭遇(おおよそ15℃以下)により花芽分化につながります。分化後の温度調節により開花を促し、ミツバチなど訪花昆虫の利用による受粉を行います。着果後には摘果および玉吊りと玉出しにより果実への太陽光の照射を積極的に行い着色を促進します。
病害虫と生理障害
前述の炭そ病が代表的な病害であり、枝葉や花、果実への感染がみられます。開花期には水分要求が高まり、潅水量も増やす必要がありますが、密閉されたハウス内では過湿によって炭そ病発生リスクも高まるため注意が必要です。換気や夜間暖房による湿度管理が重要となります。その他にも、細菌性のかいよう病、カビが原因となるうどんこ病や灰色かび病などの病害がみられます。害虫にはハダニ、サビダニ、ホコリダニ、カイガラムシなどがみられます。
果実に発生する生理障害としてヤニ果があります。果皮から果実内部の液体(細胞液)が溢れて汚れの原因となります。温度管理によって果皮の結露を防ぐことなどの対策が取られています。
潅水と施肥
マンゴーは比較的乾燥に強い作物ですが、開花期や果実肥大期には十分な潅水が必要となり、それにより適切な着花や大玉果を実現し、果実の品質向上につながります。また大型ポットを利用する根域制限栽培も一部で採用されています。週1回から3回の潅水を行い、果実肥大期には水量を増やすことで、250g以上の果実の割合を高めることができるとの東京都の報告もあります。

耐候性ハウスの頑丈なアーチ構造、巻き上げ式の遮光資材、頭上潅水用の設備などが見られる
マンゴー栽培では、春の剪定後、開花期、果実肥大期、収穫後の「お礼肥」など、計画的な施肥が欠かせません。緩効性化成肥料や有機肥料が用いられ、樹勢を維持し、翌年の収量確保を図ります。
沖縄県糸満市のマンゴー栽培と産地育成の取り組み
沖縄本島南部の糸満市はマンゴーの主要産地として、平成29年に県の拠点産地に認定されました。生産者は100名以上と多い一方で、栽培技術のばらつきや若手農家の確保が課題となり、技術向上や販路開拓、若手農家の育成などの取り組みがなされています。
地元普及センターでは主な取り組みとして、支援体制の構築や産地の意見交換会の開催に加え、部会農家や直売所出荷農家向けにマンゴー勉強会を開催しています。テーマとして「糖度を上げるため」、「色のりをよくするため」、「天敵の利用」、「ビニール開閉作業の省力化」、「まだら果対策」、「薬剤防除など」を取り上げ技術情報を共有し、あわせて現地検討会も行われています。さらに栽培管理の平準化を図るため、「マンゴー栽培管理チェックシート」を作成し、栽培ステージごとの管理作業内容とその実施時期の目安を一覧化し、作業の目的を明確化するとともに、実施状況の確認も行っています。
こうした取り組みはベテラン農家向けではなく、新規に取り組む若手農家向けのものであり、さらに天敵利用、防虫ネットの目合いの変更、葉面散布による樹勢回復、スケジュール防除と炭そ病発生状況の比較など、生産の安定に欠かせない技術面のフォローがされています。また取り組みの成果として、糖度や品質の向上により秀品率が2019年の5.9%から2021年には12%に向上したことや、産地ブランド力が強化されたことがあげられています。近年のスマート農業技術の導入では、産地全体のレベルアップのためにデータを活用した勉強会の開催が行われることも多いのですが、糸満市の取り組みは同様な考えのもとで行われていると言えるでしょう。
なお、沖縄県産の無加温栽培によるマンゴーの出荷時期は6~9月で、7月がピークとなります。
参考資料:マンゴー産地育成による地域農業の活性化、農林水産省
宮崎県のマンゴー栽培技術
宮崎県では加温栽培による早期出荷と、太陽のタマゴ(糖度15度以上、重さ350g以上で色と形が美しいという基準をクリアした最高級品)といったブランド化により、高単価での販売が京浜市場向けなどに4月~7月にかけ行われています。宮崎県のマンゴー栽培の歴史として、下記のことが良く取り上げられています(宮崎市公式ホームページ マンゴーの紹介より)ので引用します。
宮崎でのマンゴー栽培は今から30年以上前。沖縄で栽培されていたマンゴーをヒントに、お隣西都市の農家数軒からスタートしたと言われています。
マンゴーは収穫適期の判断が難しいフルーツで、早採りすると糖度が低くなり、完熟するまで置いておくと、地面に落下して商品価値がなくなってしまいます。
そこで、小さなうちからフックのついたひもで果実の着いた枝の部分(果梗)をつり上げて、日光に十分に当て、十分に大きくなり、鮮やかな赤色になり始めてからネットをかけて、その中に完熟して落ちた果実をネットでやさしくキャッチする方法によって、宮崎完熟マンゴーが生まれました。
こうしたネットを用いた収穫の簡素化は、品質向上にも寄与してきました。また近年ではポット栽培やボックス栽培(高糖度、着色促進、省力化・糖度向上)、根域制限(ベッド、ベンチ栽培:高糖度、着色促進)、ヒートポンプによる秋期夜冷(出荷早進・早期化、花芽分化促進、収量安定等)の導入も行われており、それらの例が「令和5年産宮崎県果樹栽培状況等調査」に示されています。特にヒートポンプは全県で980台(53.5ha)に導入されており、全栽培面積(81.8ha)の約65%を占めています。このように宮崎県のマンゴー栽培では、根域制限と潅水施肥やヒートポンプでの冷暖房など多様な技術が取り入れられていることがわかります。
今後の展開
マンゴー栽培の概要と主要産地である沖縄県と宮崎県の栽培技術などについてご紹介をしました。それ以外の都道府県においても、栽培面積は限られていますが、各地でマンゴー栽培が進められています。やはりマンゴーの香りや食味の魅力、商品価値の高さが、各地で栽培が広がる背景にあると考えられます。日本のマンゴー栽培は独自に進化を遂げたものであり、温暖化の影響で今後さらに栽培地域が広がる可能性があります。沖縄県のように若手農家への技術伝承を進めるとともに、品種改良や技術革新がさらに期待されます。
参考文献
・マンゴーミニ事典、JIRCASマンゴー遺伝資源サイト
・米本仁巳、熱帯果樹の栽培、農山漁村文化協会(2009)
・米本仁巳、マンゴー 完熟果栽培の実際、農山漁村文化協会(2008)

■執筆者:農業技術士 土屋 和(つちや かずお)
育苗装置「苗テラス」の開発など農業資材業界での経験を活かし国家資格の技術士(農業部門)を2008年に取得、近年は全国の施設園芸の調査や支援活動、専門書等の執筆を行っています。